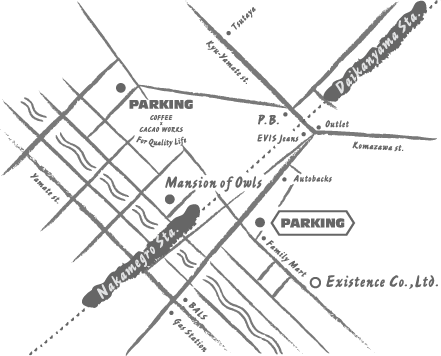マーク・ラファロが大好きだ。彼が出ているだけで、映画は傑作に見えてしまう。あれは僕が毎年のようにヴェネチア国際映画祭に出かけていた2000年夏のことだ。彼の初期のころの日本未公開作品、ケネス・ロネーガン監督の『ユー・キャン・カウント・オン・ミー』(2000) を偶然にも観ている。僕の敬愛する映画作家マーティン・スコセッシが製作総指揮していたのも大きいが、もうひとりの敬愛する映画作家クリント・イーストウッド監督作品『ミスティック・リバー』(2003) でのちに「マクベス夫人」を演じたローラ・リニーが出ていたので観たのだが、そのリニーの弟役がすばらしく良かった。この男優はとても振り幅の広い俳優である。のちにスコセッシ監督作品『シャッター・アイランド』(2010) でレオナルド・ディカプリオと共演している。去年の『はじまりのうた』(2015) の落ちぶれた音楽プロデューサーも最高だった。
『扉を叩く人』(2007) のトム・マッカーシー監督・脚本の『スポットライト/世紀のスクープ』は、全米映画俳優組合キャスト賞を受賞した、見事なアンサンブル劇である。アカデミー作品賞受賞という点が最大のセールスポイントである。つまり、同業である俳優たちがケチの付けようがないと認めたわけだ。実際に観ると涙がちょちょ切れるほどの感動作だ。すばらしい。

『はじまりのうた』のマーク・ラファロも、『バードマン/あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』(2014) のマイクル・キートンも、『きみに読む物語』(2004) のレイチェル・マクアダムスも、『マッドメン』(2007-2013) のジョン・スラッテリーも、『プラダを着た悪魔』(2006) のスタンリー・トゥッチも、『大統領の執事の涙』(2013) のリーヴ・シュレイバーも、『あの頃ペニー・レインと』(2000) のビリー・クラダップも抜群にいい。アカデミー賞会員は職業別で分けると、俳優が圧倒的に多い。つまりは、同業者の俳優たちが両手を挙げて認めた作品というわけ。どの役も、これならば「やってみたい」と思わせる、俳優の演技を観るような作品なのだ。
存在感のある彼らの服装は、特別にファッショナブルというわけではない。むしろ、なんのことはない新聞記者らしい格好が「リアル・クローズ」になっている。これがミソだ。
物語はこんなふうだ。2001年、 マサチューセッツ州ボストンの日刊紙「ボストン・グローブ」ではマーティン・バローズを新編集長として迎える。バローズはさっそく、少数精鋭の取材チーム「スポットライト」のウォルター・ロビンソンと会って、ゲーガン神父による子どもへの性的虐待事件をチームとして調査し記事にするよう持ちかける。5名のチームは取材に取りかかるがさまざまな障害や権力の妨害に会う。そして取材が佳境に入るころ、「9月11日」を迎えるのだ。

おもしろいのは、例えば5、6人で取材するシーンを撮るとすると、みな鉛筆やボールペンで必死にリーガルパッドかなんかにメモしているところだ。筆者も仕事始めは『女性自身』の「トップ屋」だったのでなにか懐かしかった。描く時代が長時間にわたっているので、その通信機器はパソコンや携帯電話に変わっていく。その変化がおもしろい。この事件を報道しようとする記者たちは、子どものころ、カソリック教徒として教会に通い、神父たちを尊敬していた。 ボストンといえば、クリント・イーストウッド作品なら『ミスティック・リバー』(2003) があるし(少年への悪戯が因果な結果を生むのは、同作品と同じだ)、マーティン・スコセッシ作品なら『ディパーテッド』(2006) があってカソリックの街である。神父たちはその教会のありがたみを利用し、一部の神父たちは少年少女たちに性的な虐待を加えていた。しかも被害者の多くは家庭環境に恵まれない、どちらかというと社会的弱者の子どもたちだった。彼らが被害を訴えても、教会のありがたみの前では無力に等しかった。またカソリック側も教区を変えるだけで、訴えは起こされなかった。
こうして何10年にわたり真実は闇に葬り去られ、被害者は増え続け、ある者は自ら命を絶ち、生き残った被害者たちもカソリック教徒が大多数の街の中でどんどん孤立していった。しかし、本作ではカソリック教会を完全な悪者に描いていない。この事件の核心に迫るなか「9月11日」に遭遇し、傷ついた人々たちに多くの宗教指導者たちはやさしく語りかけるわけだ。そういった宗教の善なる部分もちゃんと描いている。
僕は観おわって、完全に打ちのめされた。物語のラスト、「スポットライト」のチームの奔走は報われる。ラファロも、キートンも、マクアダムスも最高にいい顔だった。
『スポットライト 世紀のスクープ』
4月15日(金)より
TOHOシネマズ 日劇ほか全国公開
配給:ロングライド
Photo by Kerry Hayes (C) 2015 SPOTLIGHT FILM.
Text : Mutsuo Sato