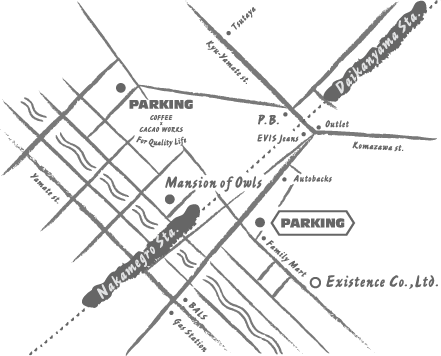トンがる事はリスクである。
端的に言えば、トンがるとは居心地の良い内輪の世界から旅立つ事ではあるまいか。生きている間じゅう、市民社会から身の回りの環境に至るまで、僕らは同じ所を行き来する。会社に勤め、アパートを借りるためには、僕らは、トンがっていない事を証明しなければならない。何より、僕たちの内面は、トンがる負担に耐えきれないのである。
『裸のランチ』の著者、ウィリアム・バロウズは1914年にセントルイスの比較的裕福な家庭に生まれる。ハーバード大学を卒業したものの定職に就くことなく、麻薬の売人として暮らした。
1997年まで続くバロウズの人生は、麻薬と男色に導かれ、創作、殺人、逃亡、治療の人生だった。ビート・ジェネレーションに属する作家の中でも、特別トンがっていたバロウズの実生活は、誰より過酷であったに違いない。
トンがる事が人生を過酷に導く一方、僕たちがトンがった物について語る際、すべての言葉は安全である。「ウィリアム・バロウズ」も「裸のランチ」も「ビートニク」も、その言葉に触れるだけで怪我をする事はない。ジャンキーで男色家の作家も、現実を離れ、現代に生きる我々が知的なテーマとして語るシーンでは、互いに本好きな事を確認する、いわば「口裏合わせ」のキーワードでしかない。
「脈絡なく錯綜する超現実的イメージ」で描かれる「『裸のランチ』」(1992年「デビッド・クローネンバーグ」により映画化された)の著書「ウィリアム・バロウズ」は「アレン・ギンズバーグ」や「ジャック・ケルアック」らとの交流で知られ、1952年には「ウィリアム・テルごっこ」の最中に妻を射殺し収監、保釈中に逃亡。「ブライオン・ガイシン」に学んだ「カットアップ」や「フォールドイン」の技法で作品を量産し、特異な世界を描いた作家である。
僕たちは、バロウズの生きた過酷さがその言葉を生み出した事を意図的に無視する事ができ、安全にウィリアム・バロウズを語る事が可能な世界に生きている。そして、彼の代表作『裸のランチ』は非常に難解な体裁であるが故に、我々にとって本好きを確かめ合うのに、より便利な一冊となった。
だが、本好き同士の「口裏合わせ」ではなく、ひとりの狂人ウィリアム・バロウズに向き合ってこその『裸のランチ』である。あなたがしばし「内輪の世界」から旅立つ一冊になる事を願ってやまない。
Text : Hiroyuki Motoori
Photo : Tsuzumi Aoyama