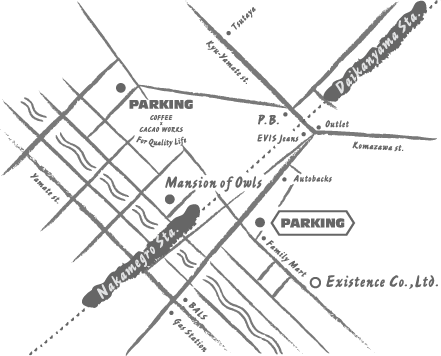地球の夜をとらえた衛星写真が伝えるように、都市とは、それ自体が発光体である。都会生活に慣れた人間にとっては、周囲から闇が失われつつある現在、もはや太陽は我々の崇める対象でなくなった。
ジョセフ・コンラッドの小説『闇の奥』は、作者自身のコンゴでの体験を基にして1899年に発表された作品である。フランシス・フォード・コッポラ監督の映画『地獄の黙示録』の原作として有名な本作だが、T・S・エリオットの『荒地』やスコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』、村上春樹の『羊をめぐる冒険』にも多大な影響を与えた作品としても知られている。近年では伊藤計劃が『闇の奥』をモチーフとして『虐殺器官』を書いた。
ポーランドの没落貴族の家に生まれたコンラッドは、作家になる以前は船乗りだった。二十代でイギリスに帰化した彼はポーランド語とフランス語を操り、作品は英語で記した。
『闇の奥』はコンラッド自身をモデルとした船員マーロウが、アフリカ奥地のコンゴへと河を遡り、非人道的な暴君でありながら魔力的魅力を持つ象牙交易の代理人クルツと対面する物語である(コッポラの『地獄の黙示録』ではベトナム戦争を舞台として翻案されている)。
19世紀、アフリカ中心部のコンゴ河流域に存在したコンゴ自由国はベルギー国王レオポルド二世の私領地だった。原住民に残虐な手段を用いて象牙とゴムの採取を強制する圧政は、植民地支配時代における人類史の〝闇〟である。本作では主人公が「魔境ともいうべき原始の自然」の〝闇〟と襲い来る原住民の「未開」の〝闇〟をくぐり抜け、ジャングルの奥地でクルツが抱く狂気の〝闇〟に近づいていく。
物語の終わり。死を迎えるクルツは「怖ろしい!怖ろしい!(原文では”The horror! The horror!”)」と最期の言葉を残した。
一体、「闇の奥」でクルツに何があったのか?本作は最後までそれを明示しない。コンラッドが船に乗り「闇の奥」に旅立つ数年前、奇しくもポーランド貴族の血を引くフリードリヒ・ニーチェは「善悪の彼岸」に記している。「お前が長く深淵を覗くならば、深淵もまた等しくお前を見返すのだ」と。
ジョセフ・コンラッド『闇の奥』は、生活の周囲から闇が失われた都会の我々にはあまりに刺激の強い作品である。無事に帰還できるよう万全の準備をされた上、覚悟を決めて読まれたい。
Text : Hiroyuki Motoori
Photo : Tsuzumi Aoyama